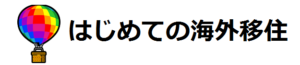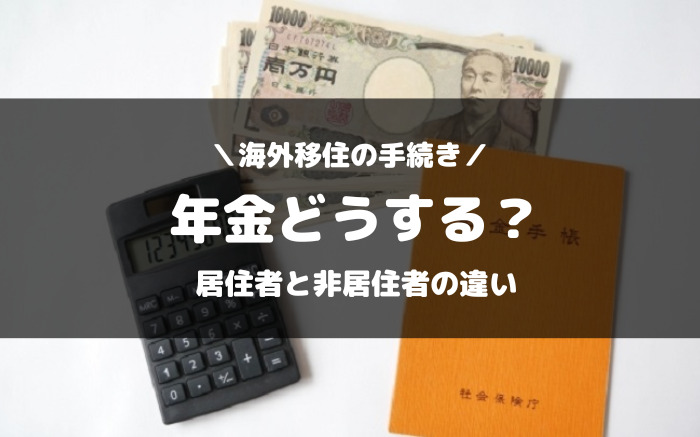海外移住をすると国民年金はどうなるのかな
海外移住をすると気になるのが、国民年金の支払いがあるのかや、将来もらうことができるのかなど。
実は、国民年金は居住者と非居住者で取り扱いが変わります。
この取り扱いによって国民年金保険料の支払いをどうするかも変わってくるので注意が必要です。
そこで、このコラムでは海外移住で国民年金や厚生年金がどうなるかを紹介します。
海外移住で国民年金はどうなる?

海外移住で住民登録を抹消して非居住者になると、国民年金は原則として脱退になります。
つまり、住民票を抜くことで国民年金の加入義務がなくなります。その代わり、国民年金保険料の支払いが不要になります。
逆に、住民登録を抹消せず住民票を残したまま海外移住をすると、継続して加入となり保険料の支払いが必要になりますね。
また、厚生年金も同様に非居住者になれば脱退になり、日本居住のまま海外赴任などで渡航される場合にはそのまま加入となります。
ただし、非居住者になっても国民年金の受給資格期間(通称、カラ期間)の対象になるので、そのまま掛け捨てになるというわけではありません。
日本非居住でも受給資格期間の対象に

日本の非居住者になると、年金には未加入になりますが、滞在中の期間は受給資格の期間に含まれます。
年金を満額受給するには25年間の受給資格期間、最低でも10年以上を満たした場合にも減額されて支給されることになりました。
そのため、年金の支給年齢に到達すると、未加入の期間(通称、カラ期間)があっても、その期間の年金分が減額されて支給されます。
ただ、受給資格の期間に含まれるとしても減額されるのには違いがないので、そこは任意での年金加入をされる方もいます。
海外移住時の国民年金の手続き
海外移住のための国民年金の手続きは、管轄の市役所などに転出届(海外転出届)への届け出だけです。
市役所などへの届け出が受理されると、自動的に国民年金は抹消されることになります。
ただ、なかには転出届を出さないまま海外に渡航される方もいらっしゃるので、その判断については下記のコラムも参考にしてみてくださいね。
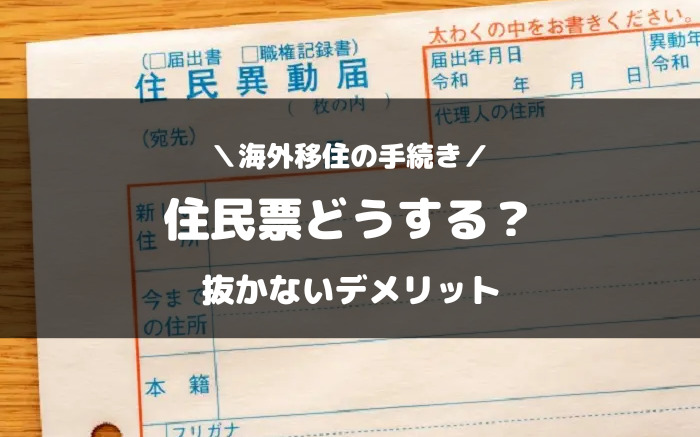
海外在住で年金を受け取る時の手続き

年金は、年金を受ける資格ができたとき自動的に支給が始まるものではなく、年金を受けるための手続き(年金請求)を行う必要があります。
これは海外でも同様です。
日本年金機構ホームページからダウンロードした年金請求書に記入の上、以下の要書類を添えて 日本での最終住所地を管轄する年金事務所へ提出する必要があります。
所轄の年金事務所に下記の書類を届け出ます。別途、身分証明書などが必要になる場合があります。
- 国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(年金請求書)
- 届書「年金の支払を受ける者に関する事項」
- 戸籍・住民票など
一般的には年金に関する書類が支給開始年齢に到達する3か月前に本人あてに送付され、申請後に原則として年金が2ヶ月に1度振り込まれます。
その際、銀行口座を現地の銀行に指定する場合には日本円から現地通貨で振り込まれることになります。
日本との租税条約の有無や内容確認
租税条約とは、簡単に言うと国同士で納税をどちらの国でするのか等を決めている条約。
例えば、条約の内容には、下記のような決め事があります。
- 協定相手国に居住している人が日本の年金を受給する場合
- 年金に対する所得税は年金条項のある租税条約を締結している場合
- 協定相手国で課税対象となり日本では非課税となる場合
まずは、海外で年金を受け取る場合は、移住先の国と日本との租税条約の内容を確認しましょう。
万が一、締結していない場合は日本と相手国の両国に税金を納めなければならない可能性も。
相手国で申請する場合は、日本年金の申請書が相手国の実施機関に備え付けている場合があります。
具体的な内容については、日本の年金事務所または年金相談センターに問い合わせしてみましょう。
海外赴任なら社会保障協定の内容確認
会社の都合で海外出向や海外赴任をしている場合は、日本と移住国との間で社会保障協定を確認しておく必要があります。
社会保障協定とは、海外に勤務する日本人を対象に年金の掛け捨てや保険料の二重払い等を防ぐ目的で国同士が取り決めです。
2019年1月の時点で、「ドイツ・イギリス・韓国・アメリカ・ベルギー・フランス・カナダ・オーストラリア・オランダ・チェコ・スペイン・アイルランド・ブラジル・スイス・ハンガリー・インド・ルクセンブルク・フィリピン・スロバキア・中国」は協定が発効済みです。
例えば、海外勤務をすると日本と源泉国(勤務先の国)で二重に社会保障制度に入ることになるので、いずれ日本に帰国する場合は無駄になってしまいます。
そこで、日本の社会保障制度を継続して、勤務先の国では年金加入を免除するなどという仕組みが取り決められています。
つまり、日本は現地国との間で社会保障協定を締結されている場合、現地国の年金制度に加入していた期間を日本の年金加入期間とみなすことができるというものです。
まずは日本と給与が発生する国(勤務先の国)に社会保障協定が結ばれているかが大切です。
但し、対象は日本に帰国することが前提なので、派遣期間の基準は原則5年以内と定められています。
過去に日本の会社から派遣されて海外勤務をされていた方は、通算期間になっているか等を日本の年金事務所または年金相談センターで確認するようにしましょう。
海外移住と国民年金のよくある質問

海外でも任意で年金加入を続けるべき?
海外移住で日本非居住者になると年金は脱退になりますが、減額されては困るという方には「任意の国民年金加入制度」を利用することができます。
別途、任意加入の手続きが公的機関で必要になりますが、日本居住時と同様に引き続き国民年金へ加入し続けることができます。
ただ、数年から数十年に渡って国民年金の支払いが必要になるため、日本での貯蓄や海外からの送金などを考慮して任意加入するかどうかを検討しましょう。
将来、海外移住先で年金は受け取れる?
海外移住の移住先でも国民年金や厚生年金などの年金を受け取ることができます。
年金は指定した金融機関の口座に2ヶ月に1度振り込まれます。その指定の銀行口座は、日本国内でなくても海外の銀行口座を指定することができます。
ただし、気を付けないといけないのは、あくまでも送金されるのは日本円です。
つまり、海外の銀行口座に振り込まれる際に「日本円→現地通貨」に外貨両替された金額で振り込まれることになります。
その際の海外送金の手数料や為替の手数料が差し引かれ、自己負担になるので、為替に左右されることも。
まとめ
今回のコラムでは「【海外移住で国民年金はどうなる?】海外在住のための手続き」を紹介しました。
海外移住で海外在住になると、日本の非居住者なら国民年金や厚生年金は脱退になり未加入になります。
ただ、将来の年金について心配な方は、非居住者でも国民年金に加入できる任意制度があるので検討してみましょう。
もちろん、海外でも年金を受け取ることができますが、為替や手数料を考慮すると年金は日本で受け取れるようにしておきたいですね。